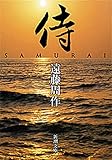遠藤周作 「侍」
沈黙、深い河を以前読んだが、三冊目に読む遠藤周作の小説である。
沈黙に続く長編、旅の物語である。
時代は沈黙よりも少し前になる。
禁制と、それに対し貿易をえさに日本への布教の再興を試みる司祭ベラスコに、同行する日本人の侍と従者はまさに翻弄されることとなる。
日本人は故国のまつりごととベラスコに翻弄されるが、ベラスコ自身もまた、イスパニアにもローマにも、やはり翻弄されていたのだった。
基本的にもちろん遠藤の価値観とは言えるが、日本人という民族へのまなざしを含め、共感することができた。
日本人の現世利益の態度、いわゆる空気を読むということのように自己を否定する習慣、民族の内部に少しでも違和感を覚えればはじき出される閉塞感など、本作の舞台の時代も、著された数十年前も、現在も、日本民族はつねにそうあったのではないかと、そう思わされるには充分なものであった。
ただしもちろん、そのような絶望だけが本筋ではない。
違和感が根底にありつつも、異邦人となってしまった日本人、故国からはじき出されたイスパニア人の内面がどう移ろったかということである。
==========
私自身のことだが、もしかしたら自分は本物の人間と異なるものなのではないかと考えていた。
脳の働きがどうやら多数の人間とは異なるのではないか。
だとしたら、脳で生きる動物である人間に対し、根本的に違う存在だと言わざるを得ないのではないか、そう思っていた。
そこから連続して、神が人を救うのだとして、もし自分が人とは根本的に異なるのなら、、、という弱気にとりつかれて、そういう考えをふりほどこうとした。
単に疑ってはならないのでふりほどこうとしたが、本作を読んでいて、その思考を完全に否定することができたと思う。
序盤、なぜ神が在ると信じるのかをベラスコは侍に問われ、
「神(デウス)がましますのは、人間一人、一人の生涯を通して御自分の在ることを示されるからでございます。いかなる者の生涯にも、神が在ることを証するものがございます。もし私が松木さまの眼に策士とうつりますならば、神はあるいは私の策士としての生き方にも御自分のましますことを示されているのかもしれませぬ」
そう答えた。
序盤、立身出世と布教の野望から動くベラスコはまさに策士という男だった。
そんな人間が、この言葉を自然に語ったことは、作中でもベラスコ自身驚いていた。
この台詞が本作を象徴するものであり、そして、私自身の存在を確かにしてくれるような、励ましてくれるような言葉だった。
私自身が多数の人間と異なり、違うものだったとしても、その生涯は、私というものを証明するためにあるのだと、そう刻むことができた気がしたのだ。
世界に写し出される私の姿はそれ自身が証明であり、だからこそ、自身について嘆き悲しみ人生を降りることほど愚かなことはないのだと、そう感じた。
そしてこの思考は、既に自分が多数派の日本人からはじき出されたからこそもてるものなのだとも思った。
作中では家、父、母、先祖というようなものを日本人の背後にある存在として描いていたが、同様なものについての言葉にすることの難しい意識は、確かに私を抑えつけている。
現在のそういう状態もまた、本作を読む態度を形作っただろう。
現在はその問題は棚上げし、逃げて保留にしている。多くの人が言うように、いつか対峙しなくてはならないのだろう。
ただ、そのような場所が私の存在理由を形作ってくれなかった以上、私は私の存在を、今からでも確固として認めなければならないのだ。
その点についてだけでも、生きることを通じて神の在ることを証明するという言葉が、大きく響いたのだった。